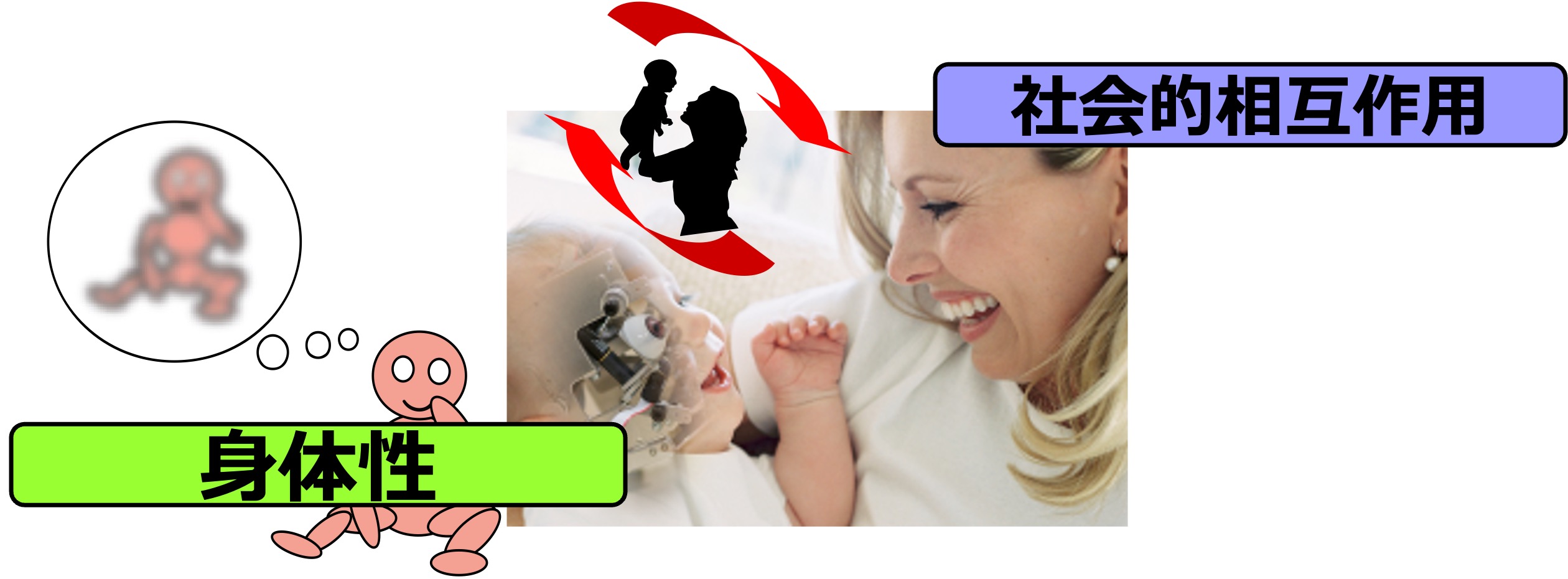認知発達ロボティクス(CDR)は、浅田稔のライフワークとも言える研究分野であり、人間の認知発達のプロセスを解明し、それをロボット設計や社会実装へ応用することを目指している。単なるAIの高性能化を超え、身体性(embodiment)や社会的相互作用(social interaction)が心の形成や意識の発達にどのように寄与するかを探る点が大きな特徴であり、神経科学、発達心理学、哲学、工学など多分野を融合する学際領域である。胎児期の運動や感覚発達から、模倣、共同注意、感情共有、そしてミラーニューロン系による他者理解の発達など、各発達段階で現れる多様な知能の萌芽をロボット実験やシミュレーションを通じて検証することで、人間理解とロボット設計の両方に貢献する。
浅田の論文[1]は、こうしたCDRの個別研究を体系的に整理し、身体性と社会的相互作用が深く絡み合いながら「自己」が形成される過程を包括的に示したもので、倫理的・哲学的課題にも言及し、CDRを人間理解の新しい科学として位置づけている。一方、もう一つの論文[2]では、Anthologyでの議論をさらに発展させ、発達が出生以前から始まるという視点や、近年のAI基盤モデルである大規模言語モデル(LLM)やVision-Language-Action(VLA)モデルのCDRへの影響を深掘りしている。巨大データに依存する現代AIへの批判として「小さく始める(starting small)」学習の重要性を再提起し、段階的学習が人間の発達の本質であることを強調する。また、この論文では、従来の身体性の概念を超え、内臓、代謝、精神プロセスなどを含む「超身体性(super-embodiment)」という構想にも言及するが、これは國吉教授(東京大学)らが提唱した概念[3]であり、浅田らはこのアイデアを取り入れつつ、抽象概念の身体的・社会的基盤の解明に挑戦している。最終的に、CDRとAGIの融合を視野に入れ、人間とロボットが相互に能力を高め合い、共生する社会の実現を目指すビジョンを描いている。
[1] Minoru Asada. Anthology: Cognitive Developmental Humanoids Robotics. International Journal of Humanoid Robotics, Vol.21, No.1, 2450002, 2024.
[2] Minoru Asada and Angelo Cangelosi. Reevaluating development and embodiment in robotics, Device, Vol.2, No.11, pp.100605, 2024.
[3] Yasuo Kuniyoshi. From embodiment to super-embodiment: An approach to open-ended and human aligned intelligence/mind. International Journal of Humanoid Robotics, 21 (01):2350029, 2024.